PR TIMESによると
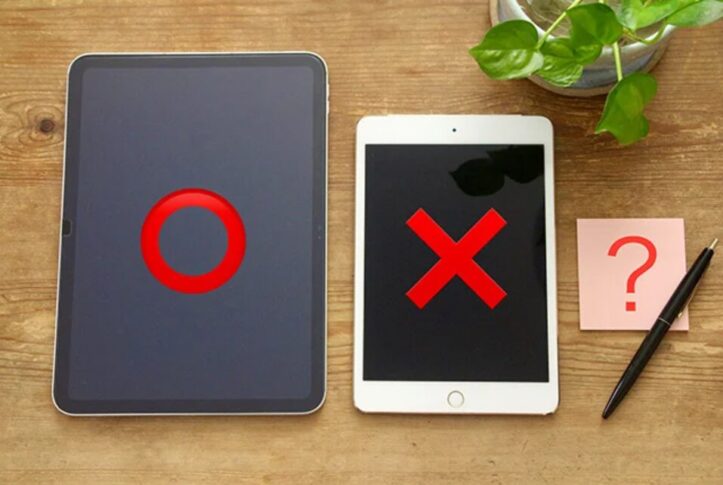
— テレビ、ポータルサイト、SNSが4割台で拮抗。選挙中のSNS規制に前向き75% —
新産業に挑戦する企業に対して政策活動やリスクマネジメントのサポートなど、パブリックアフェアーズ領域で総合的なコンサルティングを行う紀尾井町戦略研究所株式会社(KSI、本社:東京都港区、代表取締役社長:別所直哉)は、月に2回程度、時事関係のトピックを中心としたオンライン調査を行っています。
■調査の概要
昨年の兵庫県知事選ではSNS上の真偽不明情報の拡散が指摘され、選挙中のSNS規制が議論になっています。フェイスブックなどは偽情報対策として導入したファクトチェックを米国で廃止し、諸外国では子どものSNS利用規制の動きがあり、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化も加速するなど、デジタル環境は急速に変化しています。こうした状況を踏まえ、1月30日に全国18歳以上の男女1,000人を対象とした第3回オンライン調査を実施しました。
■調査結果サマリ
ニュースなどの最新情報、ポータルサイト、テレビから7割
使用しているインターネットのサービスやスマートフォンのアプリを複数回答で尋ねると、「検索」が78.3%(2024年4月18日調査80.5%)で最多となり、以下は「メール」74.5%(75.8%)、「ニュース」72.5%(77.8%)の順となった。ニュース、メールと答えた人を年代別に見ると、いずれも、おおよそ年代が上がるほど増える傾向が見て取れた。
持っているデジタル機器を複数回答で聞くと、「スマートフォン」96.9%(24年4月18日調査95.9%)が最多で、「テレビ」63.3%(59.4%)、「ノートパソコン」54.5%(55.4%)と続いた。テレビと答えた人を年代別に見ると、30代以上の層ではいずれも6割台だったが、10、20代は4割台だった。
ニュースなどの最新情報を何から得ているかを複数回答で聞くと、「インターネットのポータルサイト」77.4%(24年4月18日調査80.8%)が最多で、「テレビ」71.5%(73.0%)、「紙の新聞」34.5%(同調査では同一の選択肢なし)、「YouTubeなどの動画配信」31.7%(32.0%)、「XやインスタグラムなどのSNS」28.0%(同一の選択肢なし)と続いた。
回答を年代別に見ると、インターネットのポータルサイトとした人は、20代は4割台にとどまったのに対し、他の年代はいずれも6割を超えた。テレビ、紙の新聞とした人は、いずれも全般的に見て年代が上がるにつれ増える傾向があった。紙の新聞とした人は20代では1割台にとどまった。
20代に限定して見ると、上位3位はテレビ、インターネットのポータルサイト、XやインスタグラムなどのSNS―の順で、いずれも4割台と拮抗した。支持政党別に見ると、国民民主党はテレビが5割台と目立って低く、逆にYouTubeなどの動画配信が5割台、SNSが4割台と飛び抜けて高い特徴があった。
偽情報にだまされない自信「ない」47%「ある」43%
偽情報や誤情報にだまされない自信があるかないかを聞くと「自信がない」6.8%(24年4月18日調査8.0%)「あまり自信がない」41.4%(41.7%)、「自信がある」5.8%(4.7%)、「ある程度自信がある」37.9%(37.0%)などとなった。
選挙中のSNS規制に前向き75%
選挙中のSNS利用を「規制すべきだと思う」「ある程度規制すべきだと思う」が計75.7%に達した。
[全文は引用元へ…]
以下,Xより
【PR TIMESビジネスさんの投稿】
20代の最新情報入手は「紙の新聞から」1割台 https://t.co/LPDBJpTrZz pic.twitter.com/shq6cLZ9XS
— PR TIMESビジネス (@PRTIMES_BIZ) February 9, 2025
引用元 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000065702.htmlみんなのコメント
- 若者が新聞を読まなくなったのは当然の流れだろう。スマホがあればリアルタイムで情報を得られるのに、紙の新聞をわざわざ読む理由がない。
- テレビの影響力も徐々に低下しているのが分かる。ネットニュースやSNSの方が素早く情報が得られるため、特に若者はそちらに流れるのは自然なことだ。
- SNSを主な情報源にするのは危険だが、だからといって規制するのは問題だ。言論の自由を守りつつ、フェイクニュースを防ぐ手段を考えるべきだろう。
- 新聞はもう時代遅れになっている。情報が出るのが遅い上に、偏向報道が多いのでは信頼を失うのも当然だろう。
- メディアリテラシーを高めることが今後さらに重要になってくる。どの情報を信じるか、自分で判断できる力が求められる時代だ。
- テレビを情報源にする人が多いのは驚きだが、それも年代が上がるにつれての話。若者はもはやテレビを必要としていないのかもしれない。
- ネットの情報は玉石混交だからこそ、自分で精査する力が必要だ。新聞やテレビの情報も同様に、盲信せずに考えるべきだ。
- 選挙期間中のSNS規制に賛成する人が75%もいるのは驚きだ。だが、一方で言論統制のリスクも考えなければならない。
- 情報の真偽を見極めるのは難しい。SNSは拡散力が強い分、フェイクニュースが広がるスピードも速い。この点は社会全体で考えていく必要がある。
- メディアはSNSの影響力を恐れているのかもしれない。新聞やテレビの影響力が弱まる中で、ネットの情報をどう規制するかに注目が集まる。
- SNSの影響力が強まることで、個人が発信する情報の重要性が増している。新聞やテレビだけが情報を独占する時代は終わったのだろう。
- 新聞を読む若者が少ないのは当然だ。情報が遅い上に、一方的な主張が多すぎる。ネットの方が多様な意見を得られる。
- SNSの規制が進むと、都合の悪い情報が隠されるリスクもある。どこまで規制するべきなのか、慎重に議論するべきだ。
- 検索エンジンを利用する人が圧倒的に多いのは納得だ。自分で調べて情報を得る習慣が根付いているのは、良い傾向かもしれない。
- 新聞やテレビは、特定の思想を押し付けることが多い。それを疑問に思う若者が増え、ネットへ移行するのは自然なことだろう。
- SNSは便利だが、拡散のスピードが速いため、一度広まった誤情報を修正するのが難しい。この問題への対策は急務だ。
- ネットニュースの方が速報性が高く、情報の幅も広い。新聞やテレビの影響力が弱まるのは時代の流れだろう。
- テレビや新聞が時代遅れになりつつある今、メディア側も生き残るための改革をしなければならない。偏向報道を続けていては信頼を失うだけだ。
- 選挙中のSNS規制は慎重に議論するべきだ。悪意あるデマは問題だが、一方で自由な意見表明の場を奪うことになりかねない。
- SNSを活用して情報を得ることが当たり前になっている。若者は新聞やテレビよりも、リアルタイムで情報が手に入る方法を選ぶのは当然のことだ。
編集部Aの見解
最近の調査によると、ニュースなどの最新情報を得る手段として、20代では「紙の新聞」と答えた人が1割台にとどまった一方で、テレビやポータルサイト、SNSが4割台で拮抗していることが分かった。この結果は、若年層の情報収集のあり方が大きく変化していることを示している。
20代が紙の新聞をほとんど利用しないというのは、ある意味当然の結果かもしれない。スマートフォンが普及し、ネット環境さえあれば、リアルタイムで最新のニュースを知ることができる時代になった。わざわざ新聞を手に取る必要がないと考える人が多いのも無理はない。
特に、20代は「インターネットのポータルサイト」や「SNS」から情報を得る傾向が強い。これは、彼らがスマートフォンを日常的に使っていることとも関連しているだろう。移動中やちょっとした空き時間に、スマホで簡単にニュースをチェックできるのは大きな利点だ。
一方で、紙の新聞やテレビを主な情報源とするのは、年代が上がるほど増える傾向がある。これは、従来のメディアに対する信頼や習慣の違いが影響しているのだろう。特に高齢層は、新聞やテレビを使うことに慣れており、ネットよりも信頼できる情報源と考えている場合が多い。
また、今回の調査では、選挙中のSNS規制についても質問がなされた。75%の人が規制に前向きな姿勢を示したというのは、なかなか興味深い結果だ。SNSは情報拡散のスピードが速く、多くの人に影響を与えるが、その分フェイクニュースや偏った情報が広がりやすい。特に選挙期間中は、有権者の判断に影響を与えるため、規制を求める声が高まるのも理解できる。
実際、昨年の兵庫県知事選では、SNS上で真偽不明の情報が拡散し、問題となった。そのため、選挙中のSNS利用について規制を検討する動きが出てきている。しかし、一方でSNSの自由な議論を制限することが、言論の自由を侵害するのではないかという懸念もある。どこまで規制するべきか、慎重に議論する必要があるだろう。
さらに、SNSにおける情報の信頼性をどう確保するかという問題もある。フェイスブックなどのプラットフォームは、かつて導入していたファクトチェック機能を米国で廃止した。これは、情報の真偽を判断することの難しさを物語っている。もし誤った情報が拡散しても、それをどこまで規制するべきかという線引きが非常に難しい。
一方、諸外国では、子どものSNS利用を規制する動きも出てきている。これは、SNSが若者に与える影響を懸念してのことだ。長時間のSNS利用が精神的な影響を及ぼす可能性があることや、誤った情報に触れるリスクが高まることなどが理由として挙げられる。
また、生成AIの進化も影響している。ChatGPTのようなAIは、瞬時に文章を生成できるため、情報の拡散がさらに加速する可能性がある。もし悪意を持って利用されれば、フェイクニュースの拡散がこれまで以上に深刻な問題になるかもしれない。
このように、デジタル環境の急速な変化の中で、ニュースの受け取り方や情報の信頼性について、改めて考える必要がある。新聞やテレビのような従来のメディアに頼る人が減り、SNSやポータルサイトが主流になることで、情報の取捨選択がより個人に委ねられる時代になった。
しかし、それは必ずしも良いことばかりではない。SNSは情報の流れが速いため、じっくりと精査する時間がないまま、多くの人が情報を受け取ってしまう。これがフェイクニュースや偏向報道を助長する要因にもなり得る。
そのため、今後はメディアリテラシーの向上がますます重要になるだろう。特に若い世代は、情報を鵜呑みにせず、自分で判断する力を身につける必要がある。ニュースをただ消費するのではなく、その背景にある意図やバイアスを見抜く力が求められる。
また、選挙期間中のSNS規制についても、どこまで介入すべきか慎重な議論が必要だ。表現の自由を守りつつ、デマやフェイクニュースを防ぐためのバランスをどう取るかが鍵となる。SNSは今や多くの人にとって重要な情報源であり、規制のあり方次第で選挙結果にも影響を与えかねない。
今後、情報の信頼性をどのように確保していくのか、また、メディアの役割がどう変化していくのかについて、社会全体で考えていく必要があるだろう。
執筆:編集部A







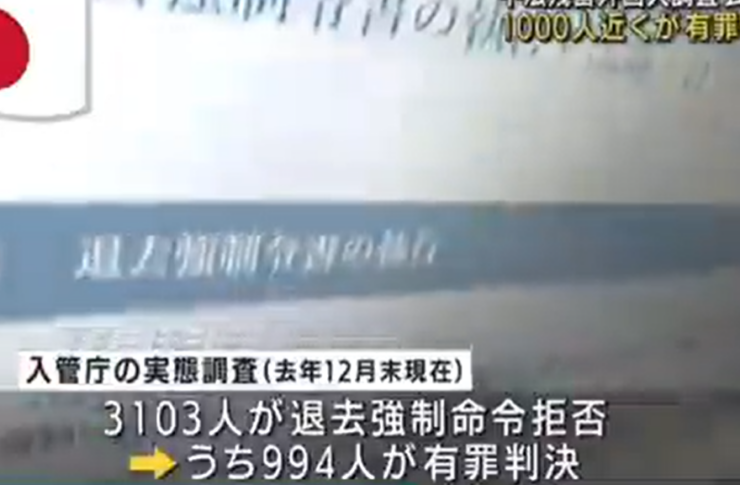










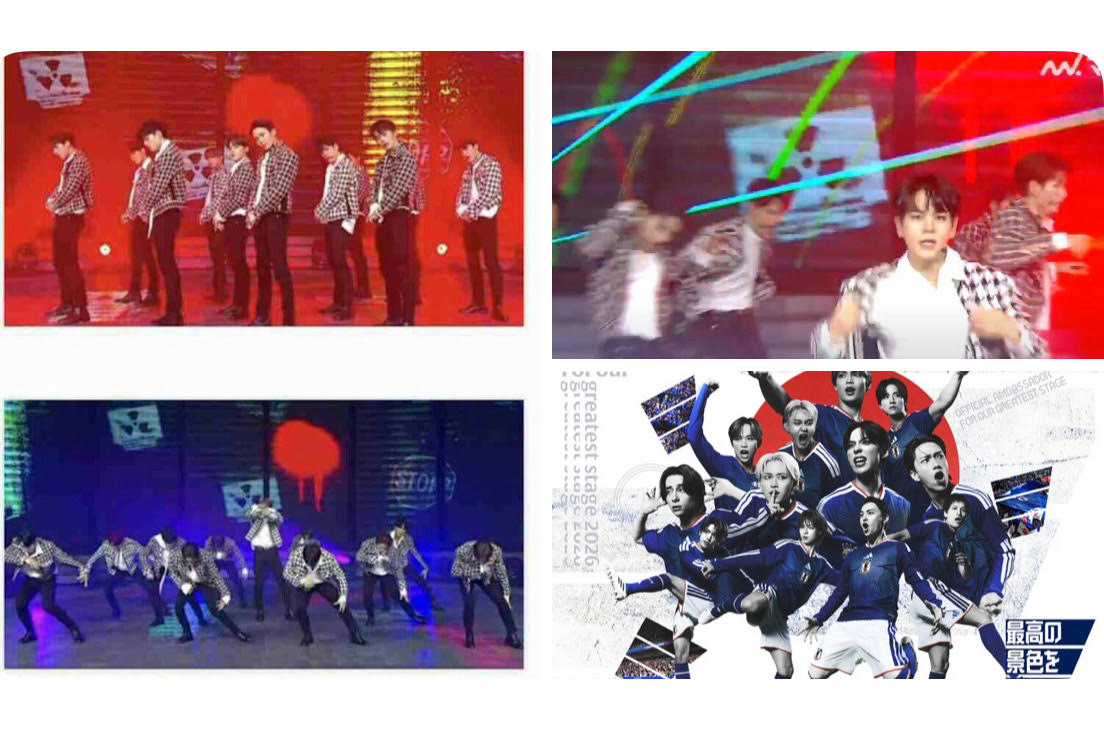












コメント