産経新聞によると
米ABCテレビは5日、中国新興企業「DeepSeek(ディープシーク)」の生成AI(人工知能)に、利用者のデータを中国政府に送る機能が組み込まれていると報じた。中国政府への情報漏洩リスクを背景に米国やオーストラリア、台湾などで広がる使用制限が加速しそうだ。
共和党のラフード下院議員と民主党のゴットハイマー下院議員は6日、米政府機関でのディープシークの利用を禁じる法案を共同提出した。声明で「中国共産党支配下の企業による米政府の機密情報入手を許してはならない」と訴えた。
ABCによると、専門家がディープシークを解析し、利用者の個人情報やインターネットの検索履歴が、中国国有の通信大手、中国移動通信(チャイナモバイル)側に送信される可能性があることが分かった。
中国外務省は企業に「データの違法な収集・保存を求めたことはなく、今後もない」と主張している。(共同)
[全文は引用元へ…]
以下,Xより

【産経ニュースさんの投稿】
「ディープシーク」生成AIに中国政府へのデータ送信機能 米ABCが報道、専門家が解析
ABCによると、専門家がディープシークを解析し、利用者の個人情報やインターネットの検索履歴が、中国国有の通信大手、中国移動通信側に送信される可能性があることが分かった。
「ディープシーク」生成AIに中国政府へのデータ送信機能 米ABCが報道、専門家が解析 https://t.co/L3oTfppl0S
— 産経ニュース (@Sankei_news) February 6, 2025
ABCによると、専門家がディープシークを解析し、利用者の個人情報やインターネットの検索履歴が、中国国有の通信大手、中国移動通信側に送信される可能性があることが分かった。
中国は嘘しか言わないから信用できない。
— Kei (@kei_haccchi) February 6, 2025
「ディープシーク」よりも「ディープセキュリティ」が必要ですね!PublicAIなら、自分のデータを守りながらAIに貢献できるよ!
— Hanamichi sakuragi (@HanamichiS57183) February 6, 2025
中華製アプリはバックドアが仕込まれてる可能性を考えたほうがいいね
— 賢にぃとギン公 (@f_fla_flat) February 6, 2025
そうやろね。という感想しかないけど…
— 邦 (@KuniDxmx666) February 6, 2025
個人情報 企業情報 国家機密
— kokoro_naki (@KokoroNaki) February 6, 2025
すべて、抜き取られます ― 🇨🇳でぃーぷしーく
東大の先生とは違うな!俺はこっちを信じる😊
— スガスガろっく (@sugasuga69) February 6, 2025
引用元 https://www.sankei.com/article/20250207-XTYZGTM2UZLWFLECZLE4FTAQEI/みんなのコメント
- アメリカと中国(日本)のプロパガンダ戦争開始
- 中華製アプリにバックドアが仕込まれてるなんて、もう驚きもしない 今まで散々やってきたことなのに、今回だけないなんてあり得ないよな
- そもそも中国がデータを収集してないとか、誰が信じるんだよ 中国外務省の否定なんて何の意味もない
- 個人情報だけじゃなくて、企業の機密データも抜かれてる可能性あるよな 使ってる企業は本当に大丈夫なのか考えたほうがいい
- ディープシークだけの話じゃないんだよな 中国製のアプリやサービスは基本的に信用しちゃいけないってことを再認識するべき
- なぜやってないと思った? 今までやってきたんだから、今回はないとか本気で言ってるなら、相当おめでたいよな
- データを抜かれたことが明らかになった頃にはもう手遅れ 利用する前にどれだけ危険か考えないと
- 中国企業は結局、中国共産党の管理下にあるんだから、政府が「やれ」と言えば従うしかない そんな企業のサービスなんて危なくて使えない
- アメリカやオーストラリアが規制してる時点で察するべきだよな あの国に甘い顔してると後悔するぞ
- 過去にHuaweiでも同じようなことがあったのに、また同じことが起きるって、学ばないやつ多すぎる
- 個人情報どころか国家機密まで抜かれる可能性あるんだから、政府レベルで対策しないとまずいだろ
- 中国は都合の悪いことは全部否定するし、証拠が出ても認めない だからこそ、最初から信用しないのが正解
- ディープシークだけじゃなくて、他の中国製AIも絶対に同じことやってるだろ ここで規制しないとどんどん広がるぞ
- 中国の技術なんて使うからこうなるんだよ 安いとか便利とかで飛びつく前に、どれだけ危険か考えろよ
- 仮に今バレてなくても、いつの間にかデータ抜かれてる可能性は十分ある 中国のアプリやサービスは本当に信用できない
- データが中国移動通信に送られてる時点でお察し ただの通信会社じゃなくて政府と一体なんだから、情報が守られるわけない
- これを「陰謀論」とか言ってるやつ、何も学んでないよな もう何度も同じことが繰り返されてるのに
- AI技術の発展はいいけど、どこが作ってるかちゃんと考えないと危険すぎる 信頼できる国の技術を使うべき
- 日本も他人事じゃないよな 中国製AIやアプリを普通に使ってる企業多いけど、本当に安全性を考えてるのか?
- こういうのを野放しにしてたら、気付いた時にはすべての情報が抜かれてる 最初から使わないのが一番の対策
- 結局、これがバレたのもアメリカの専門家が解析したからであって、中国は何があっても自分から認めることはないってことだな
編集部Bの見解
米ABCテレビが、中国の新興企業「DeepSeek(ディープシーク)」の生成AIに、利用者のデータを中国政府に送信する機能が組み込まれていると報じた。専門家の解析によると、個人情報や検索履歴が中国移動通信(チャイナモバイル)に送られる可能性があるという。この報道を受け、米国をはじめオーストラリアや台湾などでの使用制限が加速するとみられている。
米議会でもこの問題は大きく取り上げられており、共和党のラフード下院議員と民主党のゴットハイマー下院議員が6日、米政府機関でのディープシークの利用を禁じる法案を共同提出した。声明では、「中国共産党支配下の企業による米政府の機密情報入手を許してはならない」と強く訴えている。
一方、中国外務省は「データの違法な収集・保存を求めたことはなく、今後もない」と否定している。しかし、過去にも中国企業のアプリやシステムが、個人情報や機密データを不正に収集していると指摘された事例は多い。こうした経緯を考えれば、中国側の主張をそのまま信用するのは難しいだろう。
実際に、これまで中国製アプリや通信機器には、バックドアが仕込まれている可能性がたびたび指摘されてきた。例えば、かつて米国で問題視されたTikTokやHuaweiの通信機器なども、同様のリスクがあるとされ、規制の対象になっている。今回のディープシークの問題も、こうした流れの延長線上にあると言える。
特にAI技術は、個人情報や企業の機密データと密接に関わるため、セキュリティ上の懸念が高まっている。AIの学習には膨大なデータが必要であり、それがどのように利用されるかが重要な問題となる。仮にディープシークのシステムが、利用者のデータを中国の政府機関に送信しているとすれば、個人情報だけでなく、企業や政府の機密情報まで流出する可能性がある。
こうしたリスクを回避するためには、信頼できる企業や国が提供するAIを利用することが求められる。すでに米国や欧州の一部の企業は、中国製のAIシステムやアプリの使用を制限する動きを見せており、日本もこの問題について慎重に対応する必要がある。
また、政府や企業は、単に規制を強化するだけでなく、国産のAI技術を強化し、中国製に依存しない環境を整えることが重要だ。現在、日本や欧米の企業もAI開発に力を入れているが、中国の技術力も急速に向上しており、国際競争はますます激しくなっている。こうした中で、国際的な競争力を維持しながら、安全性の高い技術を確立することが、日本にとっても不可欠な課題となるだろう。
今回の報道を受け、中国側がどのような対応を取るのかも注目される。過去にも中国政府は、自国の企業に対する規制強化の動きに反発してきたが、今回も同様の姿勢を見せる可能性が高い。しかし、国際社会のセキュリティ意識が高まる中で、透明性を確保しない限り、中国製のAIシステムに対する警戒は強まり続けるだろう。
日本でも、こうした問題を他人事とせず、中国企業が提供するAIやアプリについて慎重に検討する必要がある。すでに多くの企業や個人が中国製アプリを日常的に使用しているが、そのリスクを十分に認識し、安全な選択をすることが重要だ。
執筆:編集部B



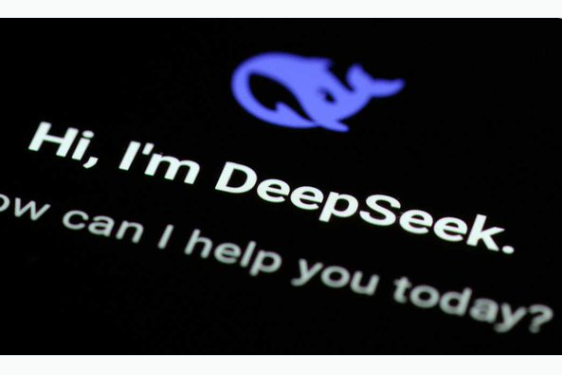














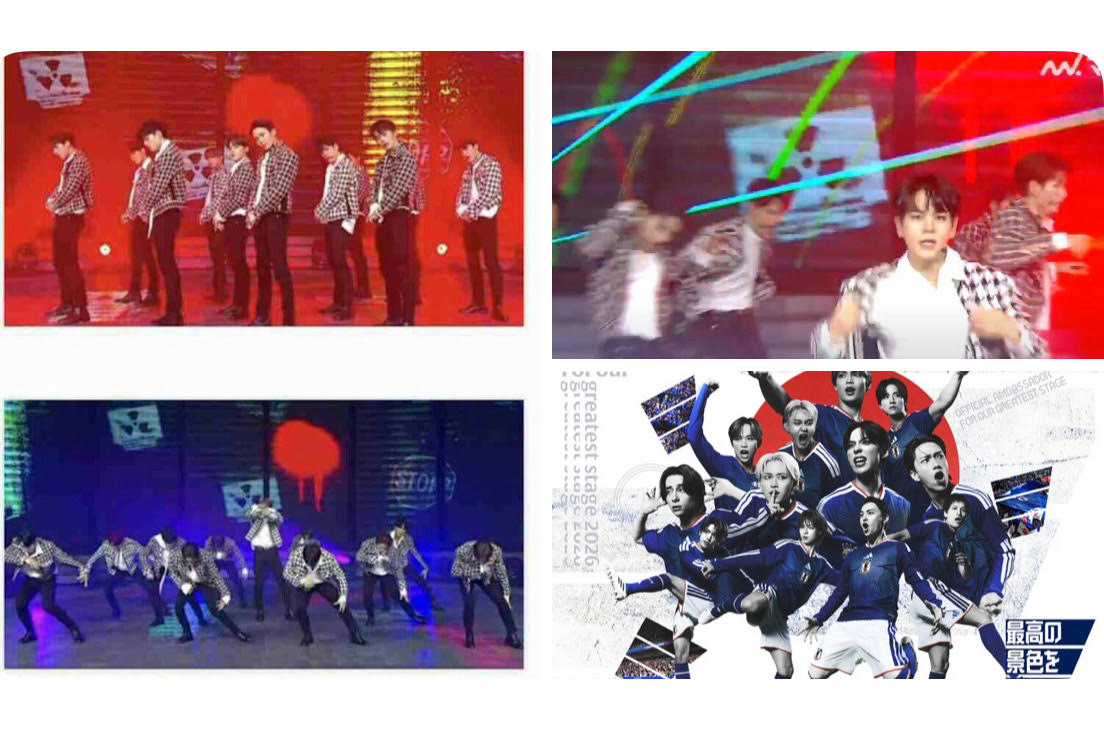












コメント