宮崎日日新聞によると
◎…宮崎市青少年プラザの階段の壁に、7色のペットボトルキャップで形作られた大きな虹が飾られている=写真。施設の雰囲気が華やかになり、利用者からも好評という。
◎…楽しみながらSDGsに取り組もうと数年前から企画。職員や利用者がペットボトル飲料を飲んだ後にキャップを集め、お茶やジュースなど色ごとに分けて貼り付けている。
◎…「冬になると集まるペースが遅くなりますが、ゆっくり楽しんでいます」と職員。リサイクルの意識とともに、施設内の虹もさらに大きく広がっていくことを願っている。
[全文は引用元へ…]

以下,Xより
【JAPAN NEWS NAVI】
【宮崎日日新聞】ペットボトルキャップで彩る虹 宮崎市青少年プラザで『楽しくSDGs』 | jnnavi https://t.co/h5g2wMRVeg
— JAPAN NEWS NAVI (@JapanNNavi) February 6, 2025
引用元 https://www.the-miyanichi.co.jp/horou/_82862.htmlみんなのコメント
編集部Bの見解
宮崎市青少年プラザで行われているペットボトルキャップを使った「虹」の装飾についての話題を見て、率直に感じたことを書いていきたい。SDGsという言葉が世の中に広まって久しいが、本当に意味のある取り組みがどれだけあるのかは疑問だ。こうした活動を見ると、表向きには環境問題への意識を高めるという目的が掲げられているが、実際のところどれほどの効果があるのだろうか。
ペットボトルキャップを集めて虹を作るというのは、一見すると子どもたちが楽しみながらSDGsを学ぶ良い機会に思える。しかし、よく考えると、これが本当にリサイクルや環境保護に貢献しているのかは微妙なところだ。キャップを集めてアートにするよりも、そもそもペットボトルの使用を減らすことの方が環境には良いはずだ。にもかかわらず、こうした活動が「SDGsの取り組み」として評価されるのは、単なるパフォーマンスに過ぎないように感じる。
また、虹色の装飾という点にも違和感を覚えた。最近、虹色はLGBT関連の象徴としても使われることが多く、こうした装飾がどのような意図で行われているのかが気になるところだ。もちろん、単純にカラフルで見た目が良いから採用されたのかもしれないが、SDGsのような国際的なテーマと絡めることで、別のメッセージが含まれているのではないかと勘ぐってしまう。
日本では、こうした「意識の高さ」をアピールする活動が盛んに行われているが、肝心の本質的な部分が抜け落ちていることが多い。世界ではすでにSDGsに対する批判的な意見も出始めている。特に欧米では、企業や政治団体がSDGsを利用して自分たちの利益を追求するケースが増えており、形ばかりの取り組みが問題視されている。しかし、日本ではいまだに「SDGsだから素晴らしい」と無条件に評価する風潮が根強く、批判的な視点が欠けているのが現状だ。
このような活動を行うのは自由だが、本当に環境問題に貢献しているのかどうかを冷静に見極めることが大切ではないか。例えば、ペットボトルの使用を減らすための具体的な取り組みを行う方が、はるかに実効性がある。しかし、それでは「見た目のインパクト」が弱く、アピールしづらいのかもしれない。だからこそ、こうしたキャッチーな活動が優先されるのだろう。
さらに気になるのは、こうしたSDGs関連の活動には利権が絡んでいることが少なくないという点だ。環境活動を名目に補助金や助成金を受けている団体も多く、実際には一部の人たちが利益を得る仕組みになっていることがある。宮崎市青少年プラザの活動がそうだとは言わないが、全国的に見ても、SDGsの名の下に公的資金が流れているケースは珍しくない。
日本では、何か新しい政策や国際的な取り組みが話題になると、それに乗じて利権を得ようとする動きがすぐに出てくる。SDGsも例外ではなく、多くの企業や団体が「SDGs対応」を掲げることで、補助金や企業イメージ向上を狙っているのが実情だ。そのため、本当に意味のある活動がどれほどあるのかは慎重に見極める必要がある。
また、こうした活動が「子どもたちの教育に良い」とされるのも気になるところだ。たしかに、環境問題について考えるきっかけにはなるかもしれないが、本当に学ぶべきことは別にあるのではないか。例えば、リサイクルの限界や、日本の廃棄物処理の現状、そもそもペットボトルの消費を減らすために何ができるのかといった、より根本的な問題に目を向けるべきではないか。単に「キャップを集めて虹を作ろう」では、表面的な学びにしかならない。
そして、もうひとつ疑問なのは、こうした活動にどれだけの時間と労力が割かれているのかという点だ。もちろん、趣味やアートとして楽しむのは自由だが、公的な施設で行う以上、それなりの目的や意義が求められるべきだろう。本当に市民にとって有益な活動なのか、それとも単なる「やってる感」を出すためのものなのか、その違いをしっかりと見極める必要がある。
結局のところ、こうした活動は「見た目の華やかさ」や「わかりやすいメッセージ性」が重視される傾向にある。しかし、本当に大切なのは、表面的な取り組みではなく、持続可能な解決策を見出すことではないか。環境問題やリサイクルの意識を高めることは重要だが、そこに本当の意味があるのかを考えることが求められる。
こうした活動が続く限り、日本はSDGsを「やっているつもり」で終わってしまうのではないか。海外ではすでにSDGsの在り方について再考する動きが出ている中、日本は相変わらず「続けることが大事」といった感覚で進めている。このままでは、世界から取り残される可能性もある。
最終的には、こうした取り組みがどれだけ実際の環境問題解決に貢献しているのかを検証する姿勢が必要だ。ただ単に「やっている」ことに満足するのではなく、実際に効果があるのか、無駄な活動になっていないかを見極めることが、これからの課題ではないだろうか。
執筆:編集部B





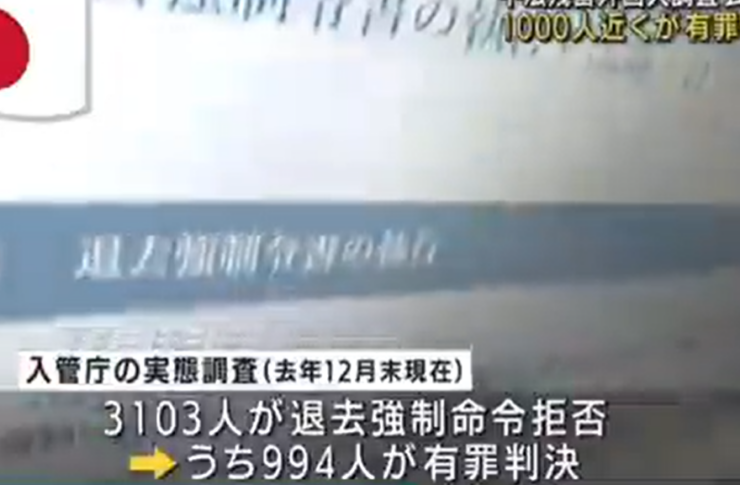












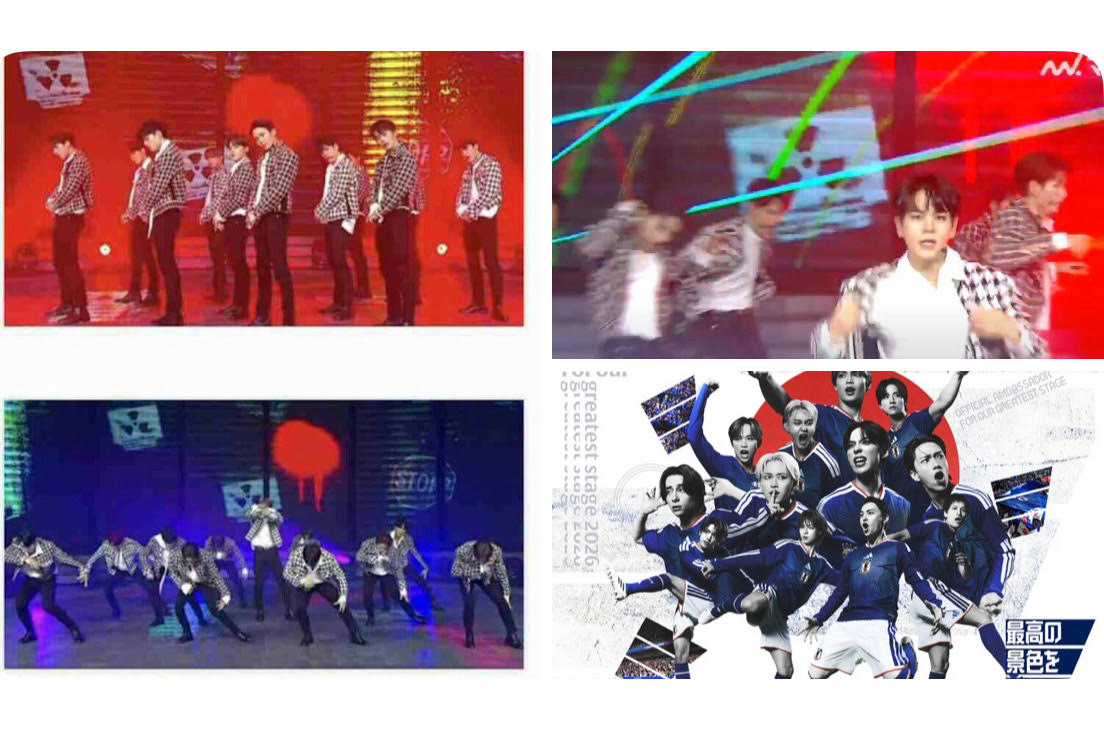












コメント