CNNによると
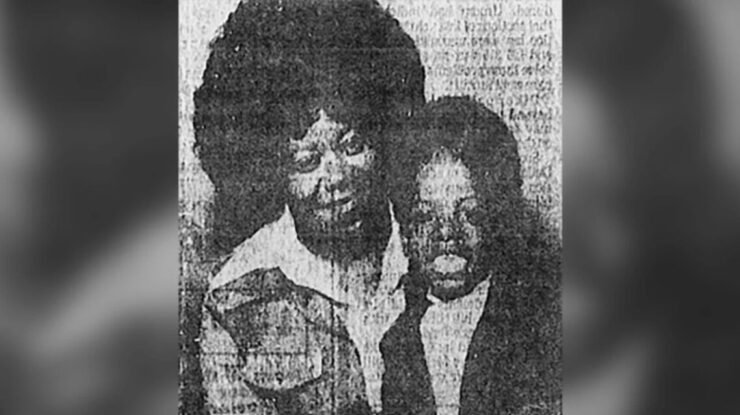
(CNN) 米中西部ネブラスカ州で40年以上前に発生した母子が犠牲になった殺人事件で、法医学上の突破口がきっかけとなり、長年にわたって容疑者と見られてきた男の逮捕につながった。同州オマハの当局が明らかにした。
逮捕されたのはアブドゥルマリク・フセイン容疑者(68)。オマハ警察によれば、フセイン容疑者は今月12日に逮捕された。デロシア・マシューズさん(26)と息子のカマルくん(7)の死に関連して2件の殺人の容疑に問われている。
警察は1979年4月24日に犠牲者の遺体を発見した。警察によれば、2人と連絡が取れず姿も見かけないのは通常ではないとして、心配する家族や友人から通報があった。
捜査員は、デロシアさんが性的暴行を受けたと判断した。2人にはロープかひもで首を絞められた痕跡が残されていたという。ダグラス郡の判事が明らかにした。
オマハ警察によれば、フセイン容疑者とデロシアさんが最初に顔を合わせたのは75年に地元で開催されたイベント。2人は知り合いになったが交際はしていなかった。フセイン容疑者は当時、容疑者として浮かんだものの、逮捕に至る十分な証拠は見つからなかった。
逮捕への糸口が見つかったのは2004年。同容疑者がコロラド州で殺人事件とは無関係の強盗で逮捕されたときだった。
フセイン容疑者のDNAが全米のデータシステムに送られた。このシステムでは有罪判決を受けた犯罪者や逮捕者、犯罪現場から集められた情報を収集している。同容疑者のDNAが犯行現場の証拠と一致したことで容疑者は逮捕された。
[全文は引用元へ…]
以下,Xより
【cnn_co_jpさんの投稿】
45年前の母子殺人事件、容疑者を逮捕 DNAの一致がきっかけ https://t.co/lPkimoamTK
— cnn_co_jp (@cnn_co_jp) February 17, 2025
引用元 https://www.cnn.co.jp/usa/35229492.htmlみんなのコメント
- 警察が当時から容疑者を把握していたのなら、もう少し証拠を集める努力ができなかったのか。時間がかかりすぎた感が否めない。
- 強盗で逮捕されなければ、DNAも登録されず、この事件は未解決のままだっただろう。別の犯罪を犯したことがきっかけで過去の罪が暴かれるとは皮肉な話だ。
- 被害者は何の罪もない母子だったのに、こんなに長い間、犯人が自由に生きていたのは許しがたい。もっと早く捕まってほしかった。
- 未解決事件はまだまだ多いはず。DNA鑑定技術を最大限活用して、過去の事件もどんどん解決していくべきだと思う。
- 犯罪者が捕まることで、未解決事件の遺族にも希望を与えられる。警察は過去の事件を積極的に再捜査する姿勢を持つべきだ。
- どんなに時が経っても、正義は実現されるべきだ。こうした事件が解決されることで、犯罪者に対する抑止力にもなると思う。
- アメリカの警察はこうして未解決事件を追い続けるが、日本でももっとDNAデータの活用を進めるべきではないか。
- 犯人が逮捕されたことで、この母子の命が無駄ではなかったと証明されたように思う。被害者のためにも、徹底的に裁かれるべきだ。
- 技術の進歩が犯罪捜査に与える影響は計り知れない。DNAデータベースの拡充と活用が進めば、さらに多くの事件が解決できるだろう。
- 過去の犯罪者も決して逃げ切ることはできない。DNA技術が発展し続ける限り、いずれは必ず捕まる日が来る。これは犯罪抑止の観点からも重要なことだ。
- 45年も経ってようやく逮捕とは、遺族にとってはあまりにも長い時間だっただろう。それでも、犯人が裁かれるのはせめてもの救いだ。
- DNA技術の進歩がなければ、この事件は未解決のままだったかもしれない。科学の力が正義を実現した事例として重要だと思う。
- 事件当時から容疑者として疑われていたのに、決定的な証拠がないから逮捕できなかったというのは、今考えると悔やまれる話だ。
- 母子2人が無惨に命を奪われた事件が、ここまで長く放置されていたのは残念だ。警察の捜査力がもっと強化されていれば、もっと早く解決できたかもしれない。
- DNAデータベースがなければ、容疑者は今も野放しになっていたかもしれない。こうした技術の活用は今後も徹底するべきだ。
- 2004年にDNAの一致が確認されていたのなら、もっと早く逮捕できたのではないか。なぜ20年近くもかかったのか疑問が残る。
- 科学の進歩によって過去の犯罪が暴かれるというのは、犯罪者にとって逃げ場がなくなるということだ。これは良い傾向だと思う。
- 遺族はどれだけ長い間、この事件の解決を待っていたのだろう。やっと真相が明らかになり、少しは心の区切りをつけられるのではないか。
- DNA鑑定がなければ、この男は一生捕まらなかった可能性がある。昔の事件でも再捜査が可能なことを示す重要な例だ。
- 犯罪者はどんなに逃げても、証拠が残っている限りは必ず捕まるということを、今回の事件が証明してくれたように思う。
japannewsnavi編集部Aの見解
45年前の母子殺人事件でついに容疑者が逮捕されたというニュースを見て、驚きとともにさまざまな感情が湧いてきた。長年未解決だった事件が、DNA技術の進歩によって解決に向かうというのは、犯罪捜査の歴史においても重要な出来事ではないかと感じる。
事件が発生したのは1979年。被害者となったのは当時26歳のデロシア・マシューズさんと、わずか7歳の息子カマルくんだった。遺体が発見された時、彼女は性的暴行を受けた形跡があり、2人ともロープのようなもので絞殺されていたという。母子がこんなにも無残な形で命を奪われたことを想像するだけで、胸が痛む。家族や友人にとっては、この45年間、犯人が野放しになっているという事実がどれほど耐え難いものだったのかと思うと、言葉にならない。
警察が当時から容疑者として目をつけていたのが、今回逮捕されたアブドゥルマリク・フセイン容疑者だ。被害者とは1975年に知り合いだったものの、交際していたわけではなく、特別な関係があったわけでもなかった。それでも事件直後から捜査線上に浮上していたのだから、当時の捜査官も彼に対して疑念を抱いていたのだろう。しかし、当時は決定的な証拠がなく、逮捕には至らなかった。
事件の転機となったのは2004年。この年、フセイン容疑者がコロラド州で強盗の罪で逮捕され、その際にDNAが全米のデータベースに登録されたことがきっかけだった。このデータが1979年の犯行現場で採取された証拠と一致し、長年未解決だった事件に進展が見られたのだ。技術の進歩によって、時を経ても犯人を追い詰めることが可能になったことは、犯罪捜査において画期的なことだと思う。
ここで改めて感じるのは、DNA技術がどれほど重要な役割を果たしているかという点だ。昔の捜査では、目撃証言や状況証拠に頼るしかなかった。しかし、科学が発展したことで、こうした凶悪犯罪の犯人を特定することが可能になった。45年という長い月日が経っても、犯人が捕まることがあるのは、まさに科学の力の賜物だろう。
とはいえ、ここで疑問に思うのは、なぜもっと早く犯人逮捕に至らなかったのかという点だ。事件発生当時、DNA鑑定技術は存在していなかったため、証拠を精密に解析する手段が限られていたことは理解できる。しかし、2004年にDNAの一致が確認されたにもかかわらず、なぜ今になってようやく逮捕されたのだろうか。DNAデータが一致した時点で、速やかに捜査が進められていれば、もっと早く正義が果たされたはずだ。この点については、捜査機関の対応に疑問が残る。
また、この事件から見えてくるのは、犯罪者が別の罪で逮捕されることで過去の犯罪が暴かれることがあるという現実だ。フセイン容疑者は強盗の罪で逮捕され、そのDNAがデータベースに登録されたことで、過去の凶悪犯罪の証拠とつながった。つまり、彼は過去の罪から逃げ切れなかったのだ。これは、犯罪者がどんなに長い間逃げ続けようとも、いずれは裁かれる可能性があるということを示している。
今回の逮捕によって、被害者の遺族がようやく真実を知ることができるというのは救いだ。しかし、45年という長い時間が経ってしまったことを考えると、遺族にとっては「なぜもっと早く?」という気持ちがあるかもしれない。それでも、犯人が裁きを受けることになった以上、少しでも心の区切りをつけるきっかけになればと願う。
こうした未解決事件が解決されるたびに思うのは、犯罪捜査におけるDNA技術の重要性と、警察のデータベース管理の精度をさらに向上させる必要があるということだ。今回のように、犯罪歴のある人物のDNAがデータベースに登録され、それが過去の未解決事件の証拠と照合されることで犯人が浮上するという流れは、今後も積極的に活用されるべきだ。過去の未解決事件はまだ無数に存在するが、DNA技術を最大限に活用することで、少しでも多くの事件が解決に向かうことを期待したい。
また、犯罪者が長年逃げ続けたとしても、必ずしも時効が成立するわけではないという点も重要だ。特に殺人事件に関しては、時効が撤廃されたケースも多く、DNA鑑定技術の進歩とともに、逃げ切れる可能性は限りなく低くなっている。今回の逮捕が示すように、犯罪者がどんなに時間を稼ごうとも、証拠は消えず、いつかは法の裁きを受けることになる。
45年という時間がかかったとはいえ、この逮捕によって、被害者の遺族が少しでも救われることを願う。そして、今後も同様の未解決事件が、科学の力によって解決へと導かれることを期待したい。事件の真相が明らかになり、正義が果たされることで、被害者や遺族の無念が少しでも晴れるよう、捜査機関にはさらなる努力を求めたい。
執筆:編集部A


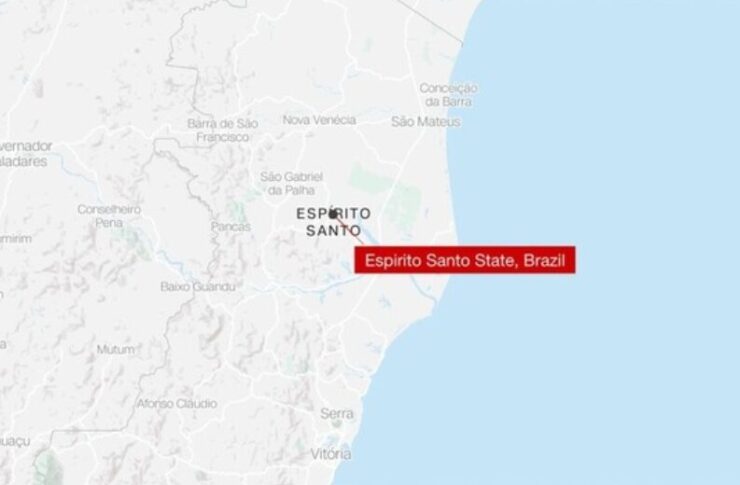















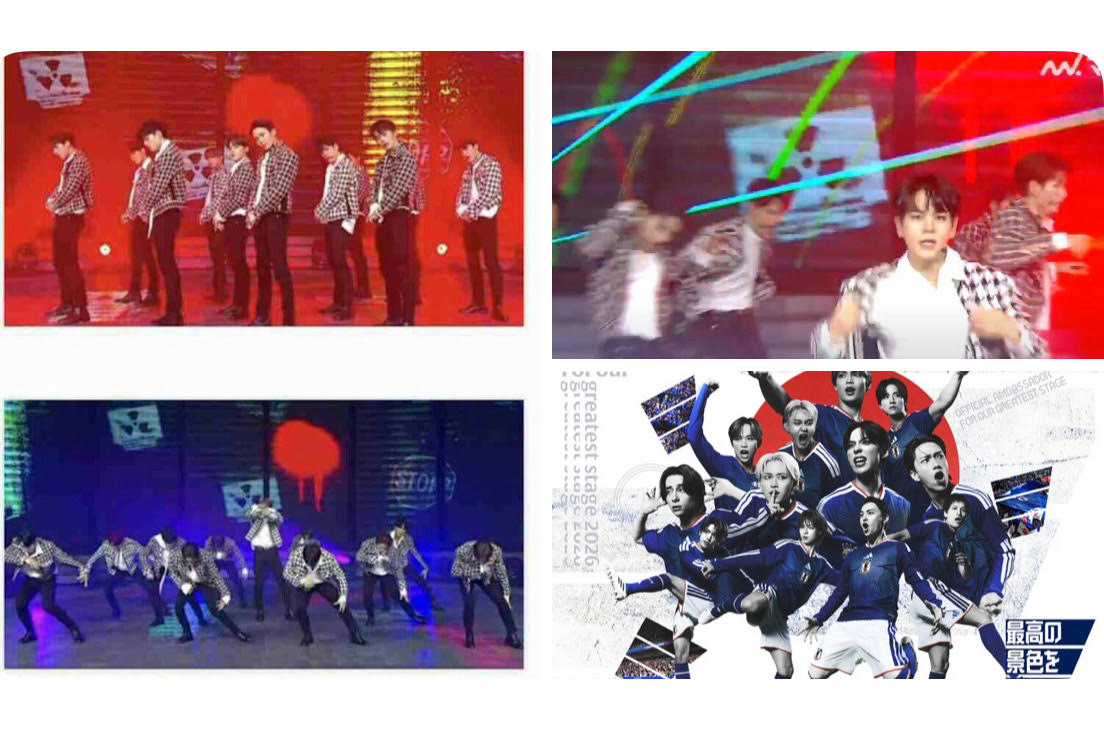












コメント