TBSによると
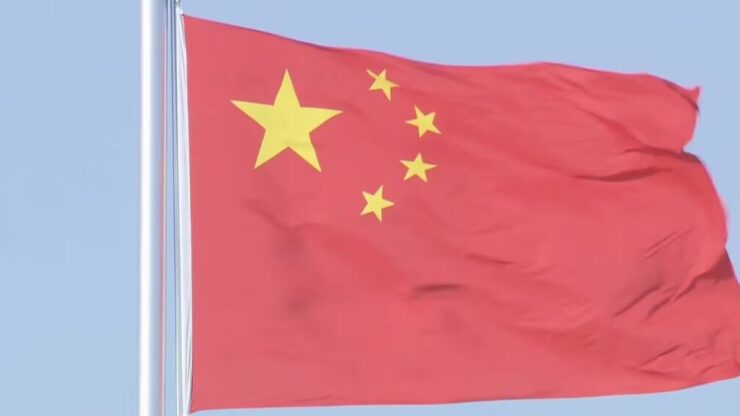
2024年の中国への外国企業からの直接投資額は45億ドル、日本円でおよそ6900億円で、前の年と比べて89%減少し、33年ぶりの低水準だったことがわかりました。
中国国家外貨管理局が14日に発表した2024年の国際収支統計によりますと、中国への外国企業による直接投資額は前の年と比べて89%減少し、45億ドル、日本円でおよそ6900億円でした。
1991年以来となる33年ぶりの低水準で、2021年の3441億ドルをピークに3年連続で急激に減少しています。
2024年の四半期ごとでは、「4月から6月期」と「7月から9月期」が2期連続で資金の流入よりも流出が上回る「流出超過」となり、通年では流入がわずかに上回る結果となりました。
中国では長引く不動産不況による景気の低迷のほか、アメリカのトランプ政権によって今後、貿易摩擦が激化することへの懸念などにより、事業の縮小や撤退を行う外国企業が相次いでいて、外資の中国離れが鮮明となっています。
[全文は引用元へ…]
以下,Xより
【KOJI HIRAI 平井宏治さんの投稿】
中国で事業展開する日本企業の経営者は、地上波すら見ていないらしい。
— KOJI HIRAI 平井宏治 (@KojiHirai6) February 15, 2025
世界中が中国から資本を引き上げていることが、中国政府発表の数字で裏付けられた。脱中国しない経営者は愚鈍
対中投資額が前年比89%減 33年ぶりの低水準 外資の中国離れが鮮明にhttps://t.co/q2dl6OAMhx
神戸製鋼は、今時、中国企業と合弁するみたいですよ。
— soyokaze (@nobenoyuki) February 16, 2025
中国で珍しくまともな統計ですね(笑)。底なし不良債権と先が見えない不況、価格競争で自分の足も食い始めた産業、外資に取っての不利な条件、スパイ防止法 等々、これじゃあ外資呼ぶの無理だよね。経団連のアホどもは訪中してるけど。
— ほら吹き男爵 (@horahukibaron) February 16, 2025
パナと資生堂を見てれば分かりそうなものやのにね😅
— いぶき (@ibuki_yoake) February 16, 2025
会社を潰すステップ
— hi-furu-chan (@nishinsoba22) February 16, 2025
あらゆる経営階層の主流は「社内政治だけ」に長けた方々
↓
社員は「誰も顧客を見ない」し
誰も挑戦しない
↓
「商品の競争力」が無くなる
↓
それでも買ってくれる「中国頼み」の経営
↓
売上の多くは中国
↓
売上が人質
↓
駐在社員が人質
↓
社員の子供が惨殺😱
媚中を辞めた国が多いのに、日本はまだまだ媚中全盛期ですよね。
— むらったー@公式アカウント (@katazugamezuki) February 16, 2025
中国に残留するのは日本企業だけになるのか!
— 宗久 (@r0OlcwRqzBx8oHQ) February 16, 2025
トヨタも単独投資により上海にEV生産工場!
これからどうなる日本経済🇯🇵
引用元 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1732320?display=1みんなのコメント
- 中国への投資がここまで急減するとは驚きだが、これまでの流れを見れば当然の結果だろう。不動産不況、規制強化、米中対立、どれを取っても外国企業が投資を避ける理由になる。
- これだけ投資が減っているのに、中国政府が有効な対策を打ち出せていないのが気になる。規制を強めるばかりでは、ますます企業が離れていくだけではないか。
- 外資の流出が続けば、中国の経済成長モデルは完全に崩れるだろう。これまで外資を頼りに発展してきたのに、今では企業を締め付けることしか考えていないように見える。
- 外国企業にとって、コロコロ変わる規制ほど厄介なものはない。安定した環境がなければ、誰も安心して投資できるはずがない。だからこそ中国から企業が逃げていくのだろう。
- 中国はこれまで「世界の工場」としての地位を築いてきたが、今やその優位性も失われつつある。人件費の高騰や規制の厳格化を考えると、もっと投資に適した国はいくらでもある。
- 投資が激減しても、中国政府は強気の姿勢を崩さない。しかし、このままでは経済の停滞は避けられない。海外企業が撤退することで雇用にも大きな影響が出るはずだ。
- 米中関係が悪化すれば、さらに状況は厳しくなるだろう。アメリカだけでなく、欧州や日本の企業も慎重になり、中国市場にこだわる理由がなくなってきている。
- 多くの企業が東南アジアへシフトしているのは、より安定した環境を求めているからだ。中国のように突然ルールを変えられるリスクを避けるのは当然の流れだろう。
- 日本企業もこの動きにしっかり対応する必要がある。中国に過度に依存するのではなく、インドや東南アジアといった新たな市場に目を向けるべき時だ。
- 外国企業にとって、一番重要なのは安心して事業を続けられる環境だ。中国はそれを提供できなくなった結果、投資が急減しているのだろう。
- 企業の撤退が相次ぐと、中国国内の雇用状況も悪化するはずだ。経済が減速し、失業者が増えれば、社会不安が一気に広がる可能性もある。
- 中国市場の魅力は年々薄れている。経済の先行きが不透明な上、規制の強化ばかりが進んでいる現状では、誰も安心して投資できるはずがない。
- 投資を増やしたいなら、まずは企業が安心して事業を行える環境を整えるべきだ。しかし、今の中国はその逆を行っているようにしか見えない。
- 日本にとっては、外資が中国から離れるこの流れを好機ととらえ、投資を呼び込む政策を打ち出すべきだ。法制度の安定性を強みにするべきだろう。
- 中国からの資本流出が止まらないのは、企業が「将来性がない」と判断しているからだ。景気が回復する見込みがなければ、誰も投資しようとは思わない。
- 政府が強引に市場を管理しようとすると、企業は逃げていく。自由な経済活動ができなければ、外国企業はリスクを避けるために他の国に移るしかない。
- 一時的な景気の悪化なら耐えられるが、ここまでの外資の逃避が続けば、中国経済の根本的な問題になってしまう。打つ手がなければ、ますます停滞するだろう。
- 中国がこのままの政策を続ければ、外資は完全に離れてしまうだろう。今後の経済成長のカギを握るのは、外国資本を引き止めることだが、今の方針では難しいのではないか。
- 日本の企業も中国市場に依存しすぎないようにしなければならない。状況が不安定な国に投資するリスクを考えれば、より安定した市場を探すべきだ。
- この投資減少の動きは、これからも続くだろう。外資の撤退が加速すれば、中国経済に与える影響はさらに大きくなるはずだ。今後の展開を注視する必要がある。
編集部Aの見解
中国への外国企業からの直接投資額が前年比89%減という衝撃的な数字を記録した。これは1991年以来の低水準であり、外資の中国離れが鮮明になっている。この動きは単なる一時的なものではなく、ここ数年続いている傾向の延長線上にある。2021年をピークに3年連続で減少しており、今後もこの流れが続く可能性が高いと考えられる。
この急激な減少の背景には、いくつかの重要な要因がある。そのひとつが、中国の不動産市場の低迷だ。長引く不動産不況により、国内経済全体が冷え込んでおり、企業にとって中国市場の魅力が薄れている。不動産業は中国経済の大きな柱であり、ここが崩れると他の産業にも大きな影響を及ぼす。経済の先行きが不透明になれば、当然のことながら、外国企業も投資を控えるようになる。
もうひとつの要因は、米中関係の悪化だ。特にアメリカでは、トランプ前大統領が再び政権を握る可能性があり、それに伴って対中政策がさらに厳しくなることが懸念されている。これまでも米中貿易摩擦が激化するたびに、中国への投資環境は悪化してきたが、今後さらに厳しい規制が設けられる可能性もある。その影響を考えれば、外資が中国から距離を置くのは当然の流れだろう。
また、中国政府の規制強化や法制度の不透明さも、外資にとって大きなリスク要因になっている。中国ではここ数年、外資系企業への監視が強まり、突然の規制変更によって事業が困難になるケースが増えている。外国企業にとって、ルールがコロコロ変わる市場は非常にリスクが高い。例えば、データ管理に関する規制が厳しくなり、外資系企業が中国でのデータの取り扱いに慎重にならざるを得なくなった。こうした環境では、新たに投資を行う企業は減るのも当然だろう。
これまで中国は「世界の工場」として、安価な労働力を武器に多くの企業を引き寄せてきた。しかし、近年は人件費が上昇し、中国の強みだったコストの低さが失われつつある。さらに、製造業においては東南アジアやインドなどが新たな投資先として注目されており、多くの企業がそちらへシフトしている。ベトナムやインドネシアのような国々は、中国と比べて規制が緩やかで、政治的なリスクも比較的少ない。そのため、外資がこれらの国へ流れていくのは自然な流れと言える。
こうした状況を考えると、中国の経済モデルは大きな転換点に差し掛かっていると感じる。これまでのように外資を引き込むことで経済成長を維持する戦略は、もはや通用しなくなっている。実際に、多くの外国企業が中国市場での事業縮小や撤退を進めている。
しかし、中国政府はこの危機をどのように乗り越えるつもりなのだろうか。今のところ、目立った対策は見られない。むしろ規制を強化し、外国企業にとってますます魅力のない市場になりつつあるように見える。このままの状態が続けば、今後さらに投資額は減少し、中国経済は長期的な低迷に陥る可能性がある。
一方で、日本企業もこの動きから教訓を得るべきだ。これまで中国市場に大きく依存してきた企業は、今後のリスクをしっかり考えなければならない。実際に、中国から東南アジアやインドに生産拠点を移す日本企業も増えており、この流れはさらに加速するだろう。日本企業にとって重要なのは、柔軟に対応できる戦略を持つことだ。特定の国に依存するのではなく、リスクを分散しながら成長を続けることが求められる。
また、日本政府もこの動きをチャンスと捉えるべきだ。多くの外資が中国を離れている今、日本に投資を呼び込む絶好の機会でもある。日本は法制度が安定しており、企業にとって予測可能な市場環境を提供できる。この強みを活かし、外国企業が日本市場に魅力を感じるような政策を打ち出すことが重要だ。例えば、法人税の引き下げや規制の緩和、労働環境の改善などが考えられる。こうした施策を進めることで、中国から撤退する外資を日本に呼び込むことができるはずだ。
今回の統計を見て、改めて中国経済の厳しさを実感した。外資がこれほどまでに逃げているという現実は、中国の成長モデルが限界を迎えていることを示しているのではないか。このまま状況が悪化すれば、中国経済はますます停滞し、世界経済にも影響を与えるだろう。
しかし、日本にとってこれは逆にチャンスでもある。中国への依存を減らし、新たな成長戦略を模索するタイミングが来ている。日本企業はこれを機に、中国以外の市場を開拓し、新たなビジネスチャンスを見つけるべきだ。
今後の動向に注目しつつ、日本がどのように対応していくのかを見守りたい。外資の流れが変わる中で、日本がどのようなポジションを取るのか、それが今後の経済成長に大きく影響するだろう。
執筆:編集部A

コメント