以下,Xより

【リサ| fashion creatorさんの投稿】
これは絶対に許されない。『中国ファスナー』の『偽造』が止まらない。 中国のサンプルに何気なく使われていた「YKKの刻印」のあるファスナー。
サンプルが中国から届いて秒で疑った。
引き手にYKKってあるけど、なんでこんな「ピカピカ」? 着てみると、引っかかってしまい、引き上げづらい。 こ、これは「偽造!!!」とすぐに分かった。
すぐにサンプル作ったに中国の工場に電話した。 つづく↓
これは絶対に許されない。『中国ファスナー』の『偽造』が止まらない。
— リサ| fashion creator (@birdgrassjp) February 1, 2025
中国のサンプルに何気なく使われていた「YKKの刻印」のあるファスナー。
サンプルが中国から届いて秒で疑った。
引き手にYKKってあるけど、なんでこんな「ピカピカ」?
着てみると、引っかかってしまい、引き上げづらい。… pic.twitter.com/t3CLBqJZl5
「中国工場」=中
私「これローカルファスナーでしょ?!」
中「そう。あったやつ使った」
私「引き手にYKKって刻印あるけどなんで?」
中「あれね、縫製工場にいっぱいあるから」
私「なんでそんなに、、どうしてなのかな?」
中「依頼があるから作ってるよ」
私「えっ?どこの企業から?」
中「それは教えられないよ」
私「今後絶対に使わないで!ほんとに」
中「わかったよ」
無法地帯の中国は、もう止められません。 これはほとんどの人は絶対的に騙されます。 こういうタブーなことが当たり前のように行われることが本当に怖いです。 我々でも背景が追えないもどかしさしかありません。
「中国工場」=中
— リサ| fashion creator (@birdgrassjp) February 1, 2025
私「これローカルファスナーでしょ?!」
中「そう。あったやつ使った」
私「引き手にYKKって刻印あるけどなんで?」
中「あれね、縫製工場にいっぱいあるから」
私「なんでそんなに、、どうしてなのかな?」
中「依頼があるから作ってるよ」
私「えっ?どこの企業から?」…
中国の「ファスナーメーカー」は増えつつあって何十社ものメーカーが存在しています。 質が良いとされている中国メーカーでも、日本のYKKの品質には到底かないません。
基本「YKK」をほぼ真似して作るので、見た目同じ様な「中国ローカルファスナー」が数多く存在しているのは確か。 ですが、引き手に「YKK」刻印」はさすがにありえない。
マネすることになんの躊躇も感じないし、むしろマネできたらエラいと思っているから。 中国ではなぜあっさりマネをするのかというと、コスパがいいから。 開発に一から考えるのはとても労力がかかることです。 マネをした方が、確実にビジネスにつなげることができるので、マネ文化が絶えない原因でもあります。
中国の「ファスナーメーカー」は増えつつあって何十社ものメーカーが存在しています。
— リサ| fashion creator (@birdgrassjp) February 1, 2025
質が良いとされている中国メーカーでも、日本のYKKの品質には到底かないません。
基本「YKK」をほぼ真似して作るので、見た目同じ様な「中国ローカルファスナー」が数多く存在しているのは確か。…
本物のYKKファスナーの見分け方↓
本物
①スライダーと呼ばれる引き手のある土台の裏面に「YKK」の刻印がある。まず裏面を要確認。
②重みがある。
③滑りがなめらか
④金属の色ににぶい深みがある(色の着いた塗装の無い場合)
⑤壊れにくい
ニセモノ
❶土台の裏面に「YKK」の刻印が無い。無印や見慣れない刻印がある。
❷軽い
❸滑りわるい
❹妙にピカピカしている(色の着いた塗装の無い場合)
❺壊れやすい
古い歴史のある日本の産業は中国には真似ができない「技術」がある事を忘れないで欲しい。
本物のYKKファスナーの見分け方↓
— リサ| fashion creator (@birdgrassjp) February 1, 2025
本物
①スライダーと呼ばれる引き手のある土台の裏面に「YKK」の刻印がある。まず裏面を要確認。
②重みがある。
③滑りがなめらか
④金属の色ににぶい深みがある(色の着いた塗装の無い場合)
⑤壊れにくい
ニセモノ…
偽造ファスナーがレベルを上げているので注意! pic.twitter.com/nHIdsdJhQY
— リサ| fashion creator (@birdgrassjp) February 1, 2025
種明かししてしまうと、より精巧な模造品がでてきてしまう気がします。
— tokumeikibon 原発再稼働・新型原発を! (@tokumeikibon1) February 1, 2025
罰金払うことになっても儲けと売名効果の方が勝るんだから中国からしたらやり得な状況なんですよコレ…
— 炙りT次郎 (@fhikodead02) February 2, 2025
日本の家電メーカーも最終的に技術並ばれて価格破壊に対抗出来ずに崩壊した
中国が在る限りどれだけ新技術を開発してもコピーして潰されるって事を日本はもっと深刻にならないと不味いんですよね…
引用元 https://x.com/birdgrassjp/status/1885794372249440706?s=51&t=y6FRh0RxEu0xkYqbQQsRrQみんなのコメント
- 偽造品がこんなにも簡単に流通している事実に驚きを隠せない。消費者はどうやって本物を見分ければいいのか。
- 中国では偽造が当たり前になっている状況が恐ろしい。こうした文化が改まらない限り、問題は解決しないだろう。
- 正規品と見た目がほとんど変わらない偽物が出回っているのだから、普通の人が気づけるわけがない。
- 日本のブランドの信頼を損なう偽造品は、国内だけでなく世界中の市場にも悪影響を及ぼすことになる。
- ファスナー一つでも、品質にこだわる日本のメーカーが努力しているのに、それを無視した偽造品が出回るのは許されない。
- 偽造品の取り締まりをもっと厳しくしなければ、日本の製品に対する信頼がどんどん失われていくだけだ。
- 中国の工場が平然と偽物を作っているという事実に衝撃を受ける。これではビジネスの公平性が保たれない。
- 偽造品を使っている消費者が被害を受けるだけでなく、日本のメーカーが無駄な損害を被る状況は問題だ。
- 偽物の品質が低いことは明らかで、消費者の安全にも影響を与えかねない。この問題は深刻だ。
- 日本の製品が高品質であることを誇りに思っているだけに、こうした偽造品の流通は特に許せない。
- 中国での偽造品の製造が止まらない理由は、結局のところコストが安いからという短絡的な考えに過ぎない。
- 偽造品が簡単に手に入る環境を放置すれば、日本企業だけでなく、消費者もその被害を受け続けることになる。
- 日本のブランドが世界で信頼される理由は、品質に対する徹底したこだわりがあるからこそ。それを偽物が壊している。
- これからも偽造品が出回るなら、日本の企業が中国で事業を展開すること自体がリスクになるのではないか。
- 偽造が普通に行われる社会では、真面目に品質を追求している企業が馬鹿を見てしまう。それが一番問題だ。
- 中国での偽造品製造に対する取り締まりが弱い限り、日本だけでなく世界中のブランドが危険にさらされる。
- 偽造品が当たり前のように作られることで、正規品を作っている人たちの努力が無駄になる。それが許せない。
- 偽造品を平気で使っている工場や企業がいる限り、本物の価値が正当に評価されることはない。
- 日本の技術と品質が評価されているからこそ、偽造品がそれを真似している。しかし、それは本物の価値を奪っているだけだ。
- 偽造品問題を放置すれば、いつか必ず大きなトラブルにつながる。今こそしっかり対策を取るべきだと強く思う。
編集部Aの見解
中国でのYKKファスナーの偽造が止まらないという話には、強い危機感を覚えた。実際に中国から送られてきたサンプルを確認したところ、YKKの刻印が入った偽物だったという事実には驚きを隠せない。YKKといえば、日本を代表するファスナーメーカーであり、世界的にも高い信頼を得ているブランドである。それにもかかわらず、中国では堂々と偽物が流通し、それが当たり前のように受け入れられていることは問題ではないかと感じる。
今回の件で特に印象的だったのは、中国の工場の対応だ。サンプルを送ってきた工場に確認したところ、「縫製工場にたくさんあるから使った」と平然と言われたという。つまり、中国ではYKKの偽造品が当たり前のように出回っており、縫製工場では特に疑問を持たずにそれを使っているということになる。さらに「依頼があるから作っている」との発言も見逃せない。どこかの企業が積極的に偽造品を発注しており、それがビジネスとして成り立ってしまっているのだ。
そもそも、本物のYKKファスナーと偽物のファスナーには明確な違いがある。本物は耐久性が高く、長期間使用してもスムーズに動く。しかし、偽物は見た目こそ似せていても、実際に使用すると引っかかったり、すぐに壊れたりすることが多い。今回のサンプルも、「ピカピカしていて怪しい」と感じたことが偽物を見破るきっかけとなったようだ。つまり、品質にこだわる人が注意深くチェックすれば違いに気づくことはできるが、一般の消費者はなかなか見抜けないだろう。
この問題の背景には、中国のビジネス文化が関係していると思う。中国では、独自に開発するよりも、既存のものを模倣してコストを抑えるほうがビジネスとして合理的だと考えられている節がある。だからこそ、偽造品の製造が後を絶たないのだろう。特に、世界的なブランドのロゴやデザインをそのままコピーして販売することに対して、罪の意識が薄いのではないかと感じる。中国では、マネできることが「すごいこと」と考えられており、独自の技術を開発するよりも、他社の成功した製品を真似るほうが手っ取り早いという発想が根付いているのだろう。
こうした状況に対して、日本企業はどのように対応すべきだろうか。まず、偽造品が出回らないようにするために、徹底した監視体制を敷く必要がある。YKKのようなブランドは、既に厳格な品質管理を行っているが、それだけでは不十分だ。例えば、偽造品を扱っている企業を特定し、法的措置を取ることが求められる。しかし、中国の法律では知的財産権の保護が十分ではなく、訴えを起こしても思うように処分が下されないケースもあるため、より厳しい対応が必要かもしれない。
また、日本国内の消費者も、偽造品を見抜く目を養うことが大切だ。正規品を購入する際は、信頼できる販売店を選ぶことが重要であり、価格が極端に安い場合は疑ってかかるべきだろう。特にオンラインショッピングでは、偽造品が混ざっている可能性が高いため、購入前に口コミや販売元をしっかり確認することが欠かせない。
さらに、日本政府もこの問題に対して積極的に関与すべきだ。知的財産権の侵害に対する取り締まりを強化し、日本企業が安心して事業を展開できる環境を整える必要がある。近年、中国との経済関係はますます深まっており、貿易の規模も拡大している。しかし、こうした偽造品の問題が続く限り、日本企業のブランド価値が損なわれ、ひいては日本経済全体にも悪影響を及ぼしかねない。
今回のYKKファスナーの偽造問題は、決して単なる一企業の問題ではない。これは、日本のモノづくりの信頼性を揺るがしかねない事態だ。日本の技術力と品質が世界に誇れるものであるからこそ、こうした偽造問題には断固として対処しなければならない。企業、消費者、政府が一体となって、偽造品の流通を防ぐ努力を続けることが求められる。
私たちは、安価な偽物に騙されず、本物を選ぶ目を持つべきだ。そして、日本企業も、中国に対してより強い姿勢で対応する必要がある。偽物の流通を許せば、日本の製造業の信頼が損なわれ、結果として日本経済全体に影響を与えることになる。だからこそ、この問題に対して、より厳格な監視と対策を講じるべきだと強く感じた。
執筆:編集部A





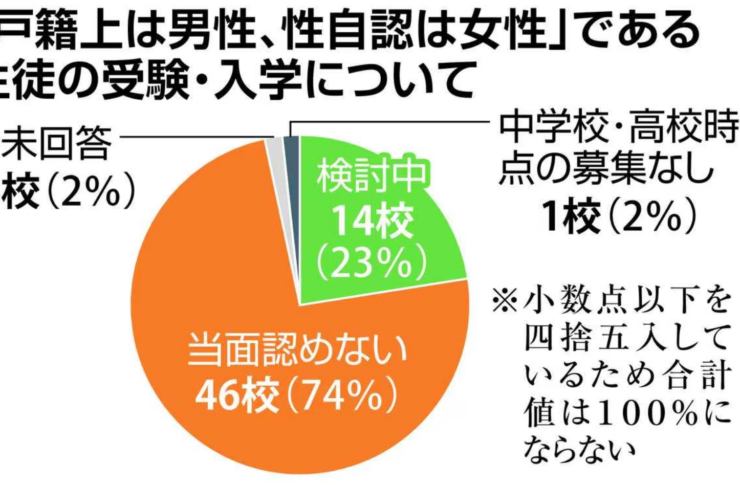

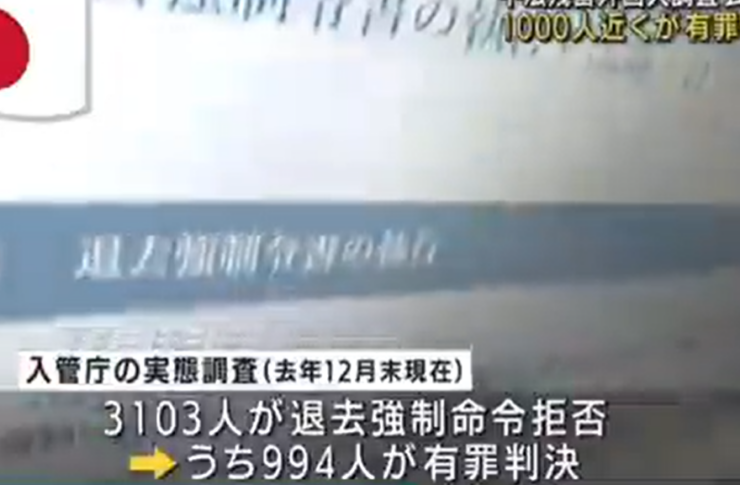










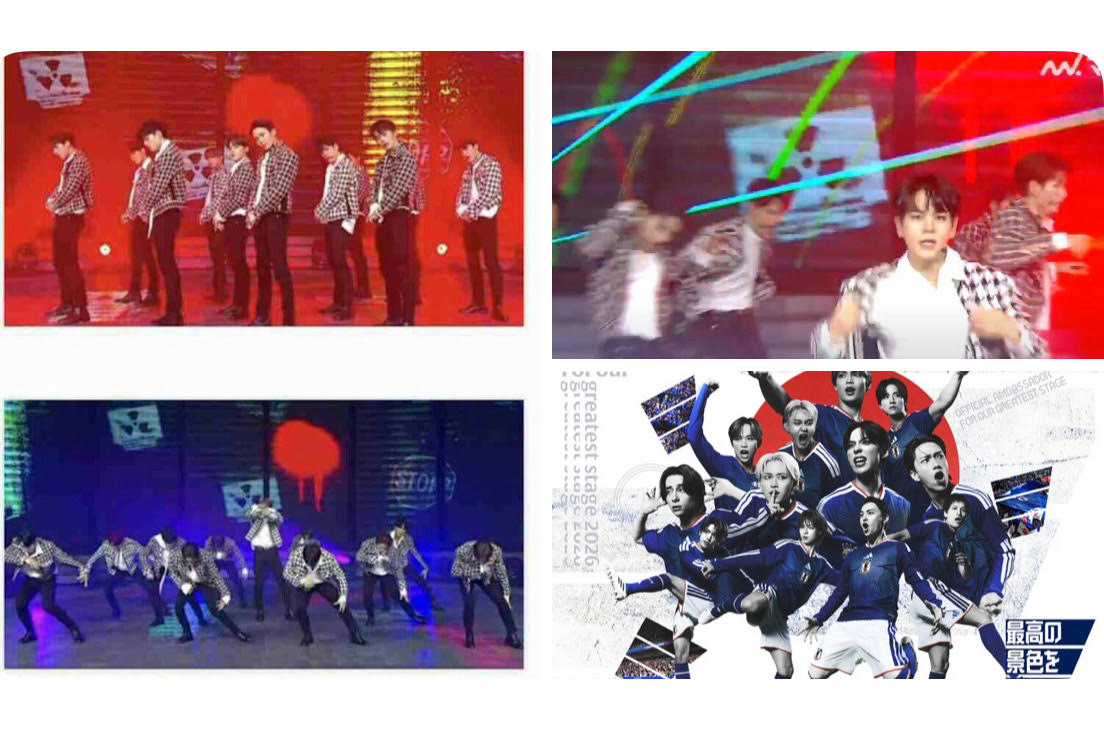












コメント